もう二年近くもここには何も書かずにきてしまったけれど、最後に書いたのはアントニオ・マリンを修理に出した話だ。そして、今日二年ぶりに書くのも、アントニオ・マリンの話。というのも、先月3月30日にギタリストの長谷川郁夫さんと2本のアントニオ・マリンによるギター二重奏という贅沢な経験できたから。長谷川さんとはYouTubeチャンネルを通じてちょこちょこと交流を続けてきたのだが、昨年末、長谷川さんから「デュオをやりませんか」とのお誘いをいただき、ぜひぜひ…という運びになった。
実はここが二年近くもご無沙汰になっていたのは、私が何十年ぶりという引っ越しに追われていたというのも一つの理由で、それはようやく去年の夏にひと段落した。しかし、実家仕舞いでもあったその引っ越しは相当に大変で、結局片付けきれずに新居まで持ち込んでしまったガラクタも多々あり、片付けは今も終わっていない。そんなこともあって、お話をいただいてから実現するまで3ヶ月余りかかってしまったが、その間に二重奏の曲を決め、練習し、撮影環境を整えてはいた。
そうして臨んだ3月30日当日、なんとか表向きは片付けたスタジオに長谷川さんがやって来た。1975年のアントニオ・マリンを携えて。実は長谷川さんとは直にお会いして言葉を交わしたことは、ほとんどない。もう10数年前と思うが、私の勤め先にあるGGショップにいらしていたときにスタッフに紹介してもらったのが最初。長谷川さんはご存じのはずもないが、私は長谷川さんのブログを密かに愛読していたので、「勉強させていただいてます」とかなんとか挨拶したような記憶がある。その後、何度か顔を合わせることはあったものの、結局はYouTubeを通じて親しく?なったようなもので、まぁ面白い時代ではある。
そんなことはさておき…。アントニオ・マリン二重奏の話。動画をご覧いただければわかるけれど、長谷川さんのマリンは、いわゆるブーシェマリンではない。一方私のマリンは、2006年作の”モデロB”、すなわちブーシェモデルだ。いわゆる「ブーシェマリン」というのは、アントニオ・マリンがフランスの名工、ロベール・ブーシェのモデルを元に設計したタイプのギターを指す。アントニオ・マリンがブーシェに出会ったのは1970年代後半と言われていて、この邂逅によりマリンのギター造りは大きく変わったとされる。
今回、長谷川さんにお持ちいただいたマリンは、ブーシェとの邂逅以前の、異なるタイプのもの。時期的にはブーシェマリン前夜ともいうべき時期の作だ。長谷川さんによると、日本に入っているアントニオ・マリンの多くはブーシェマリンで、それ以前の前期型ともいうべきタイプのこのマリンはむしろ珍しい、とのこと。そこら辺の経緯については動画の中で長谷川さんのお話が聞けるので、興味のある方は是非。
そして、気になる実際の音について。これも動画内で楽器の持ち替え有りの弾き比べをしているので、ご覧いただくのがいちばん…なのだけれども、簡単にまとめると、驚くほどよく似た音、という印象。「弾き心地」は違う。タッチの返り方や音の立ち上がりに、それぞれの個性があって、弾けば違いはすぐにわかる。しかし、特に二重奏の演奏中に隣から聞こえてくるもう1本のマリンの音は、やはり「マリンの音」。構造が違おうと、弾き手が違おうと、弦が違おうと、なんなら長谷川さんは指頭奏法なんだけど…、そんなことはおかまいなし、マリンの音なのでした。そして、そんな2本のマリンの音は軽やかに混ざり合って、とけるようなブレンド具合。弾いてる私がいちばん幸せかも…と思える二重奏体験でした。
とはいえ、これは聴く人によっても印象が変わるかもしれない。今書いたように、「弾いてる私には」そんな風に聞こえるということであって。ただ、いずれにせよこれはつまり、作家はやっぱり作家の音を持っているんだなぁ…という、言われてみれば当たり前かもしれないこと。そんなことをあらためて実感した楽しい二重奏体験でした。対談(前後編)と共に二重奏のみの動画も公開しているので、ぜひYouTubeでご覧ください。長谷川さんはギターの、ことに楽器の話となると話し出したらとまらない…というくらいいろんなことをご存じで、そんな尽きない話の泉のごく一部ではありますが、楽しんでいただけるかと思います。
早速、次の二重奏は…なんて話も出ているので、乞うご期待!…(練習しないとね、私は😨)
アントニオ・マリン2本、弾き比べ対談(前後編)&二重奏(ソル&カルリ)の動画はこちら
▶️長谷川郁夫さんとコラボ再生リスト

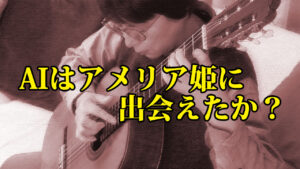


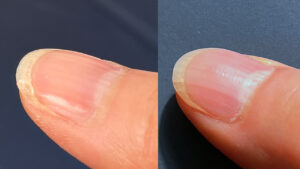

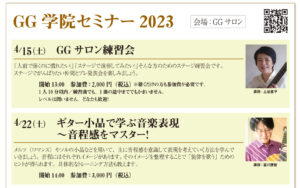

コメント